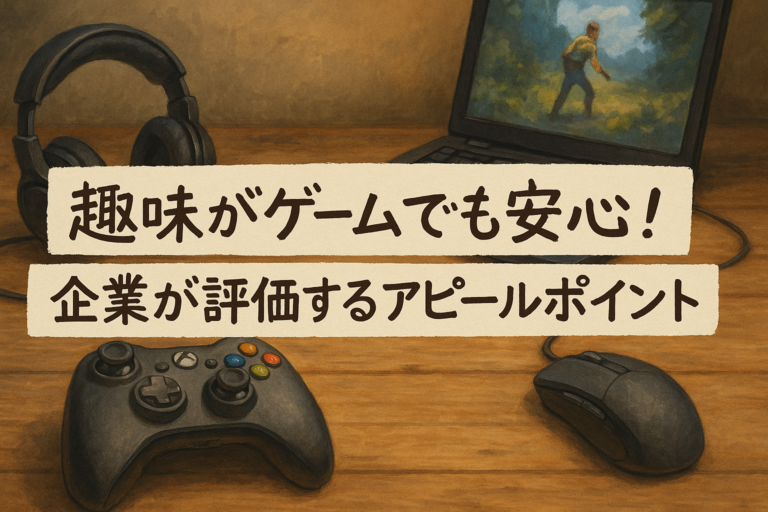趣味がゲームでも安心!社会人や大人が自己成長・交流・リフレッシュを同時に叶えられる、注目の新作・モバイル・eスポーツゲームを厳選紹介!ビジネス力も高まる一作が見つかります。
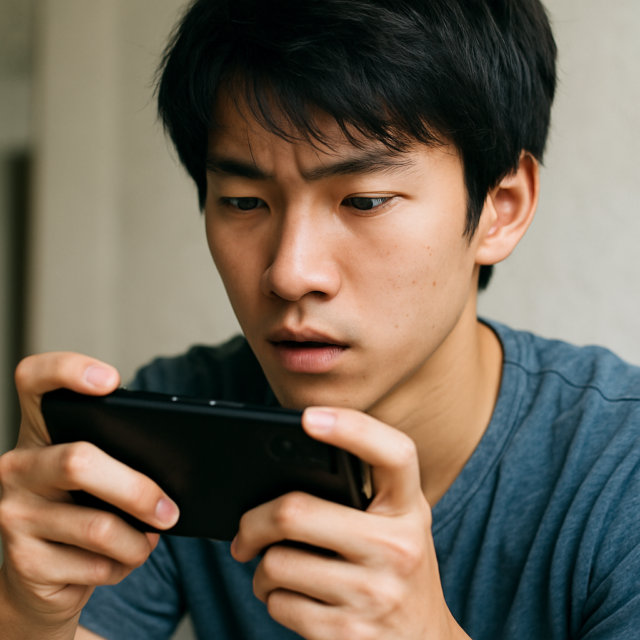
趣味としてのゲームが企業に与えるポジティブな印象

企業が求める趣味の概要とその重要性
近年、採用現場において「趣味は何ですか?」という質問の意味合いが大きく変わってきています。以前であれば単なる雑談や人柄を知るための軽い問いかけに過ぎませんでしたが、今は「その人がどんな価値観を持ち、日々どのような姿勢で物事に取り組んでいるか」を判断する重要な要素とみなされています。
例えば、ゲームが趣味であることを申告した場合、昔は「遊んでばかりのイメージ」「根暗そう」などとネガティブに受け取られることもありました。しかし、現代社会ではその印象は大きく変化しつつあり、特にIT業界やベンチャー企業、クリエイティブ分野では「デジタルリテラシーが高い」「新しいもの好き」「流行や最先端技術への適応力がある」といった、むしろプラス評価を受けやすくなっています。
なぜ企業は趣味に注目するのでしょうか。それは、趣味を通じて「自主性」「継続力」「課題発見力」など、社会人に必要な資質やスキルが自然に身につくことが多いためです。自分の時間をどう過ごしているか、何に熱中しているかから、その人の「仕事観」や「人柄」が垣間見えるのです。単なる息抜きやストレス発散のための娯楽というだけでなく、趣味が自己成長や社会性の向上につながっているかどうかを、企業はしっかり見極めようとしています。
ゲーム趣味がもたらすスキルと成長の可能性
実際に「ゲームが趣味」と言っても、その中身は多種多様です。家庭用ゲーム機やパソコン、スマートフォン、最近ではVRやARを活用した最先端のゲームも普及しています。ゲームのジャンルも、パズルやアクション、RPG、スポーツ、シミュレーション、eスポーツまで幅広く、遊び方や関わり方によって得られる経験やスキルも異なります。
まず、現代の多くのゲームは単なる暇つぶしではありません。たとえば、オンラインで世界中の人と協力したり対戦したりするタイプのゲームでは、「コミュニケーション能力」「協調性」「リーダーシップ」「戦略的思考」「判断力」「瞬時の対応力」「忍耐力」など、社会で必要とされる多様なスキルが磨かれます。
例えば、チーム制のシューティングゲームやRPGでは、メンバー同士で役割分担を決め、目的達成のために計画を立て、時にはリーダーとしてグループをまとめる必要があります。ここで問われるのは、まさに「リーダーシップ」「マネジメント力」「調整力」など、社会人として求められる要素そのものです。実際、ゲームでの経験を活かして仕事でもプロジェクトリーダーやマネージャーになったという方も少なくありません。
また、困難なミッションや高難易度クエストに挑戦する際は、何度も失敗しながら「なぜ上手くいかなかったのか」「どうすればクリアできるのか」を考え抜き、試行錯誤を繰り返します。こうした経験は「課題解決力」「論理的思考力」「創造力」を養うのに非常に役立ちます。自分で情報を集めたり、他人の成功事例を研究したり、時には全く新しいアプローチを試みたりすることで、「自分で学び取る力」や「自分を成長させる姿勢」が自然と身についていくのです。
加えて、eスポーツのような競技性の高い分野では「目標設定力」「計画力」「集中力」「メンタルコントロール」「フィードバックを受けて改善する力」なども求められます。大会に出場したり、上位ランクを目指して日々練習を重ねたりする中で、勝ち負けに一喜一憂しながらも粘り強く努力することは、ビジネスの現場でも大きな財産となります。
企業に好印象を与えるためのアピールポイント
企業に良い印象を持ってもらうためには、単に「ゲームが好き」というだけでなく、「どのようなスキルや価値観を得たのか」「自分がどんな成長を感じたのか」を具体的に伝えることが重要です。例えば、以下のような視点やエピソードを意識して自己アピールをしてみましょう。
・「オンラインゲームのクランリーダーとして、10人以上のメンバーのスケジュールを調整し、目標を共有しながら、意見の違いをまとめて結果を出した経験がある」
・「新しいゲームタイトルの攻略方法をいち早くキャッチし、効率的なプレイ方法を自分なりに分析・共有することで、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献できた」
・「大会への出場経験を通じて、目標に向けて努力し続ける大切さや、失敗から学び取る姿勢を身につけた」
また、ゲームを通じて「相手の気持ちを尊重する」「分かりやすく物事を説明する」「失敗を恐れず挑戦する」「一つの目標に向けてメンバーをまとめる」といった社会人として求められるスキルを身につけていることをアピールすると、面接官や採用担当者の印象はぐっと良くなります。
さらに、情報収集力やITリテラシーの高さも大きなアピールポイントです。ゲームを深く楽しむためには、インターネットを活用して攻略情報や新しいアップデート情報を集めたり、英語で海外サイトを調べたりする力も求められます。これらの経験を通じて、デジタル時代に欠かせない「自ら学ぶ力」や「情報を使いこなす力」を身につけていることも、企業側にとっては大きな魅力になります。
また「対人ゲームでマナーを守ってプレイしている」「長時間の作業でも集中力を保てる」「趣味仲間とオフラインイベントを企画・運営したことがある」なども立派なアピール材料です。大切なのは、あなたがゲームを通じてどんな成長を遂げ、どのように社会や仕事に還元できるかをしっかり伝えることです。
履歴書や自己PRでのゲーム趣味の活用法

履歴書にゲーム趣味を記載する際の具体的な書き方
履歴書の「趣味」欄に単に「ゲーム」とだけ書くのは、やや印象がぼやけてしまいがちです。より良い印象を残すためには、ゲームのどんな点に魅力を感じ、どんな経験やスキルを得ているかを一言添えるのがおすすめです。
例:
・「戦略系オンラインゲームを通じて、仲間と協力しながら課題解決やチーム運営のスキルを培っています」
・「eスポーツ大会への出場経験があり、目標設定や努力の継続、PDCAサイクルを意識した取り組みを大切にしています」
・「情報収集を活かし、新作タイトルの攻略方法を分析・発信しています」
また、履歴書の自己PR欄でも、ゲーム趣味をどのように仕事に活かせるかを積極的にアピールしましょう。「ゲームを通じて身につけた問題解決力や継続力を、業務においても役立てたい」といった前向きな姿勢を言葉にすることで、採用担当者の印象がぐっと良くなります。
ゲーム趣味を面接で効果的にアピールする方法
面接で「趣味はゲームです」と話す際には、できるだけ具体的なエピソードや体験談を交えて伝えることが重要です。たとえば、「オンラインゲームのリーダーを務め、メンバーをまとめて難易度の高いミッションをクリアした経験がある」や「失敗を繰り返しながらも根気強く挑戦し、最終的に目標を達成できた」という実体験は、説得力が増します。
また、ゲームを通じて得た気づきや学びを、仕事の現場にどう生かしたいかを話すのも効果的です。「コミュニケーションの大切さを実感した」「目標達成に向けてコツコツ努力することの大切さを知った」「多様な価値観の人と協力することで視野が広がった」など、ゲームで得た成長ポイントと仕事で求められるスキルを結び付けて話すことで、面接官に好印象を与えることができます。
さらに、趣味を聞かれて答える際に不安な場合は、ゲームジャンルや関連するスキルに言い換えて伝える方法もおすすめです。たとえば、「戦略ゲームで論理的思考力を磨いている」「協力型ゲームでチームビルディングの経験を積んでいる」「海外プレイヤーと交流しながら英語力や異文化コミュニケーションを強化している」など、仕事にも応用できるスキルとしてアピールすることが可能です。
面接官が気になるゲーム趣味の言い換え例
「ゲーム」そのものが悪い印象を持たれる時代は過ぎつつあるものの、よりビジネスライクでポジティブに伝えるために、以下のような言い換えもおすすめです。
・「戦略型シミュレーションゲームを通じて、論理的思考力と状況判断力を磨いています」
・「チーム制のオンラインゲームでリーダー経験があり、調整力やマネジメント力を身につけました」
・「海外プレイヤーとの交流を通して異文化理解や語学力を高めています」
・「eスポーツ活動を通じて、目標達成に向けた継続的な努力や自己成長の大切さを学びました」
このように、具体的なジャンルやスキル、体験を織り交ぜて表現することで、単なる趣味を超えて“ビジネスにも通じる強み”として伝えることができます。特に「どんな力がついたか」「その力をどう活かしたいか」を自分の言葉でしっかり説明できると、他の応募者との差別化にもつながります。
さらに、ゲームを通じた「分析力」「情報発信力」「イベント企画力」「ネットワーク作り」なども仕事に直結するスキルとしてPR可能です。たとえば「コミュニティ運営で意見の集約やイベント企画をした経験」や「自分のプレイ体験をSNSやブログで発信していた」といった実績も、現代の企業活動において十分評価されるポイントとなります。
ゲーム趣味が社会人に与える影響と対策

仕事におけるゲームの活用方法と必要性
現代社会において、ゲームは単なる娯楽の枠を大きく超えています。特にデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む日本のビジネスシーンでは、ゲームに親しむこと自体が、時代の流れや新しい技術への感度、そして柔軟な思考を養うきっかけにもなっています。
まず第一に、ゲームを通じて身につく「情報処理能力」は、多忙な社会人にとって非常に大きな武器となります。たとえばアクションゲームやRTS(リアルタイムストラテジー)、MOBAなどは、刻々と変化する状況に素早く反応し、最適な選択肢を瞬時に判断しなければなりません。こうした経験は、職場での突発的なトラブル対応や、顧客との商談、複数タスクの同時進行など、実社会のあらゆる場面で活きてきます。
さらに協力型のオンラインゲームやeスポーツで養われる「コミュニケーション力」「リーダーシップ」「チームビルディング力」は、会社という組織で成果を出すために欠かせない資質です。ゲーム内での役割分担、戦略立案、メンバーへの声かけやサポート経験は、実際のプロジェクトマネジメントや後輩指導にも直結します。「自分がどのポジションで最大限力を発揮できるか」「状況に応じて誰かをサポートする柔軟性」など、ゲームならではの学びが実社会でも重宝されるのです。
また、現代のゲームはインターネットと直結し、グローバルな環境でプレイすることが当たり前となりました。世界中のプレイヤーと協力や対戦をする中で、英語を始めとする語学力や異文化理解、国際的なマナーやコミュニケーション術も自然と身につきます。海外クライアントや外国籍スタッフと接する機会が増えている現代社会では、このような「異文化適応力」も強いアドバンテージになります。
そして、ゲームは「リフレッシュの手段」としても極めて優秀です。社会人は日々多くのストレスを抱えがちですが、短時間でも没頭できるゲームの世界に触れることで脳と心がリセットされ、翌日のパフォーマンスが向上したという声も少なくありません。単なる息抜きにとどまらず、適度な“ゲーム時間”が長期的な仕事の成果や健康にも良い影響をもたらします。
就職活動におけるゲーム趣味の影響と対策
就職活動や転職活動の場面で「趣味がゲーム」と答えることにためらいを感じる方も多いでしょう。確かに、一部の伝統的な業界や年配の面接官には、まだ“ゲーム=遊び”という固定観念が残っている場合もあります。しかし、現代の就活・採用現場では、「ゲームを通じてどんな能力を伸ばしてきたか」「その経験をどう仕事に活かせるか」をしっかり説明できれば、むしろ大きな武器になります。
たとえば、戦略シミュレーションや協力型RPGで得た「状況判断力」「目標達成力」「計画力」「対人調整能力」は、職種を問わずビジネスで活きるスキルです。「チームを率いてイベント攻略を成功させた」「トラブル発生時に仲間をまとめて問題解決に導いた」など、実体験を交えて自己PRできると、他の応募者と大きく差をつけることができます。
加えて、最近はeスポーツの大会出場経験や、動画配信・SNS運営など「発信力」「企画力」「ネットワーク形成力」も高く評価されます。もし面接でマイナスに受け取られそうな空気を感じたら、「課題解決力」「学び続ける姿勢」「デジタル時代の情報活用力」など、どんな企業でも求められる普遍的な資質に結び付けて伝えるのが効果的です。
また、履歴書の趣味欄には「ただゲーム」と書くのではなく、「協力型オンラインゲームを通じてチームワークやリーダーシップを身につけました」「eスポーツの大会参加をきっかけに継続力や計画性を高めました」など、具体的な成長ポイントやエピソードを添えると好印象を与えやすくなります。
ゲームを通じた友人とのコミュニケーション能力の向上
ゲームは今や“個人の娯楽”から“人と人をつなぐコミュニティ”へと進化しています。とくに社会人になると、新たな友人や人脈を作る機会が激減しがちですが、ゲームを通じて年齢・職種・地域・国籍を超えた多様な仲間と出会うことができます。こうしたゲームコミュニティは、現代社会の「つながり不足」を補う大切な場にもなっています。
オンラインゲームでは、仲間と協力して目標を達成したり、チャットやボイスチャットを活用して意見交換したりする過程で、「傾聴力」「説明力」「交渉力」「相手の立場への配慮」といった対人スキルが自然と鍛えられます。たとえば、意見が食い違ったときに冷静にまとめ役を務めたり、新しい仲間にルールや攻略法を分かりやすく教えたりした経験は、職場での後輩指導やリーダー業務にも必ず役立ちます。
また、ゲーム内でのオフ会やリアルイベントを主催・運営することで、イベント企画力や調整力、全体を見渡すマネジメント力まで磨かれることも珍しくありません。社会人になってから「人付き合いが苦手」「会話が続かない」と悩んでいた方が、ゲームを通じて自然にコミュニケーションが得意になったという声も多く、自己肯定感や社会性の向上にも大きく寄与しています。
ゲームがきっかけで実際に結婚したり、転職や起業に発展したりといった“人生の転機”を迎える人も少なくありません。まさに現代型の「新しい人間関係の構築手段」といえるでしょう。
ゲーム趣味を通じた自己成長の具体的なエピソード

趣味が仕事に活かされた体験談
ゲームでの経験が仕事に大きく活かされた例は数え切れません。
たとえば、IT系企業で働くAさんは、学生時代から続けてきたオンラインゲームでギルドマスター(クランリーダー)を担当していました。数十人規模のチーム運営を任され、目標設定、役割分担、日々の進捗管理、時にはトラブル対応もこなす中で、自然とリーダーシップやマネジメント力が身につきました。入社後は、新人研修やプロジェクトの進行管理を任されることが多く、上司や同僚からも「まとめ役」として信頼される存在となりました。
一方で、Bさんは戦略型シミュレーションゲームに熱中し、自分で効率的な攻略法やパターンを分析し、仲間と共有することに楽しさを見出していました。この「分析力」と「情報発信力」が評価され、仕事では業務改善提案やマニュアル作成、社内勉強会のリーダーを任されるようになりました。Bさんは「ゲームでの試行錯誤や他人との連携がなければ、今の自分はなかった」と語ります。
また、動画配信やSNSでの発信活動を行っていたCさんは、その経験を活かして会社の広報チームや新規サービスの立ち上げにも参加。コンテンツ制作やマーケティングの分野で新しいキャリアを切り拓きました。自分の趣味や特技を、ビジネスに直結するスキルに転換できた好例といえるでしょう。
ゲームに熱中することのプラス面と発散機会
社会人は日々の業務や人間関係、将来への不安など、さまざまなストレス要因に直面します。
そんな中、ゲームは“短時間で確実にリフレッシュできる”“日常から離れて没頭できる”という大きなメリットがあります。脳科学的にも、好きなことに集中する時間は脳を活性化し、メンタルの健康にも良い影響を与えることが分かっています。
また、ゲームは「失敗を前向きに捉える力」や「諦めず何度もチャレンジする精神力」を育てる場でもあります。高難度のクエストや対人戦で何度も負けても、そのたびに新しい攻略法を考え、反省し、挑戦を繰り返す――この過程は、まさに仕事でのPDCAサイクルと同じです。
困難にぶつかったときも「まずはトライしてみる」「分析して改善を繰り返す」という姿勢が自然と身につきます。
ただし「やりすぎ」「依存」には注意が必要です。仕事や生活リズムを崩さず、計画的に“メリハリ”をつけてゲームを楽しむことが、社会人にとって最も大切な“発散機会”の活かし方といえるでしょう。
自身の経験を交えた成功事例の紹介
私自身も、社会人になってからゲームを通じてさまざまな成長や成功体験を重ねてきました。
オンライン協力型ゲームで初めてリーダーを任されたときは、不安も大きく、うまくメンバーをまとめられず失敗も多くありました。しかし、メンバーの意見をじっくり聞き、自分なりの言葉で目標や戦略を伝えるうちに、次第に信頼が生まれ、チームの結束力も高まっていきました。
この経験が、仕事でのプロジェクト進行や会議ファシリテーションに大きく役立っています。意見が対立したときも冷静に話し合いの場をつくり、全員が納得できる解決策を模索する癖がつきました。
また、日々のゲームで鍛えた情報収集や課題解決のスキルが、実際の業務改善や新規提案にもつながり、上司や同僚から「頼れる存在」として頼りにされるようになりました。
このように、ゲーム趣味は自己成長の“トレーニングの場”としても、社会人生活を豊かにする“コミュニケーションの場”としても、計り知れない可能性を秘めています。重要なのは「どんな学びや成長があったか」を自分自身の言葉で具体的に語れること。あなた自身のゲーム体験を自信に変えて、ぜひこれからのキャリアにも活かしてください。
ゲーム趣味を持つことのメリットとデメリット

趣味としてゲームを持つことの評価と理解
ゲームを趣味とすることに対する世間の評価は、時代や世代によって大きく変化しています。かつては「ゲーム=子供の遊び」「時間の無駄」と見なされることもありましたが、今や多くの大人や社会人も積極的にゲームを楽しみ、その価値を再評価する流れが強まっています。
特にIT業界やクリエイティブ分野、グローバルビジネスの現場では、ゲームで培われる論理的思考力・反射神経・コミュニケーション力・情報収集力などが大いに評価される時代です。
一方で、今でも「ゲームばかりしていては社会性が身につかない」「時間管理ができない人と思われるのでは」と不安を感じる方も少なくありません。
大切なのは“趣味として適度に楽しむ”“自己管理ができる”“ゲームで学んだことを現実世界で活かしている”という点を自分の言葉で説明できることです。
たとえば「協力型ゲームでリーダー経験を積み、実際の仕事にも役立てている」「ゲーム内で得た友人関係が実生活の交流に発展した」など、体験に基づいた具体的なエピソードが説得力を生みます。
社会人としてのバランスを保つためのアプローチ
社会人がゲーム趣味を最大限に活かすには、“バランス感覚”が非常に重要です。ゲームに夢中になるあまり生活リズムや仕事のパフォーマンスを崩してしまうのは本末転倒。
自分で「何時以降はゲームをしない」「休日だけ集中して遊ぶ」「目標をクリアしたら必ず休憩を取る」など、明確なルールを作り、それを守ることで、健康的な趣味ライフを維持できます。
また、仕事や人間関係でストレスが溜まったときの“リフレッシュ手段”としてゲームを位置付けるのも有効です。気分転換ができれば仕事の効率も高まり、前向きな気持ちで日々を過ごせます。
家族やパートナー、友人とも「一緒に遊ぶ日を決める」「趣味について理解を深め合う」など、周囲とのコミュニケーションも大切にしましょう。バランスを意識することで、趣味と仕事・プライベートを両立させやすくなります。
趣味さえあれば面接での不安を減らすための考慮事項
面接で「趣味はゲームです」と答えることに迷いを感じる人は多いですが、ポイントは“どのように伝えるか”です。
単に「毎日何時間もゲームをしています」と話すより、「ゲームを通じてどんな学びや成長があったか」「社会人としてどのように活かしているか」を明確に伝えることで、ネガティブな印象は一気に払拭されます。
たとえば「オンラインゲームでリーダーを務め、メンバーをまとめてプロジェクトの目標達成に貢献した経験」「新しいジャンルのゲームに挑戦し続けることで得たチャレンジ精神」など、エピソードを交えて話すのが効果的です。
趣味を持っている人は“自分なりの楽しみを見つけられる力がある”“ストレスを上手に発散できる”というプラスの評価につながるため、堂々と自分の趣味をアピールしましょう。
結論: 趣味としてのゲームを活用したアピール戦略

ゲーム趣味の適切な印象を持つための戦略
趣味がゲームであることをプラスに伝えるためには、「自己成長」「社会性」「チームワーク」「自己管理」「多様性」など、ビジネスで求められる要素と結びつけることがポイントです。
例えば、「チームでの協力や目標達成経験」「難関クエストを乗り越えるための粘り強さ」「情報を素早く収集し、効率的に活用する能力」「異文化コミュニケーションを楽しめる柔軟性」など、仕事や社会生活でも役立つ力を明確に言語化しましょう。
また、履歴書や自己PRでは“単なる娯楽”としてではなく、「自分にとってゲームとは成長と交流の場である」「困難に挑戦する姿勢や人とのつながりを大切にしている」などのメッセージを込めると、採用担当者に好印象を与えられます。実際に仕事で活きた体験談や、社会人生活におけるプラス面を具体的に語ることで、趣味を強みに変えることができます。
これからの働き方における趣味の役割
働き方改革やリモートワークの普及により、「オンとオフの切り替え」「心身の健康維持」「多様な人材との交流」が重視される時代です。
その中でゲーム趣味は、集中力や判断力の向上、チームワークやリーダーシップの強化、ストレスコントロール、さらには新しい人間関係の構築など、幅広い役割を果たすことができます。
今後は、趣味が「自己表現」や「社会的価値」としてますます注目されるようになります。自分の趣味を自信を持って語れる人は、変化の激しい時代にも柔軟に対応しやすく、企業側からも“主体性のある人材”として期待されるでしょう。
趣味を仕事や生活の原動力にすることで、より充実した社会人生活を実現できます。
コミュニケーションツールとしてのゲームの可能性
ゲームは単なる個人の楽しみを超えて、コミュニケーションツールとしても大きな可能性を持っています。オンラインでの協力プレイや対戦は、年代や国籍・業種を超えた人々とのつながりを生み、リアルな出会いやビジネスのチャンスにつながることも珍しくありません。
たとえば「ゲーム仲間がきっかけで新しいビジネスプロジェクトが始まった」「オンラインゲームのイベント運営で企画力や調整力が高まった」など、現代型の交流や自己表現の場としてゲームが果たす役割は年々拡大しています。今後もゲーム趣味を通じて、新しい人脈や学び、自己成長の機会がどんどん広がっていくでしょう。
このように、趣味としてのゲームには多くのメリットと一部の注意点がありますが、自己管理とバランスを大切にすれば、社会人としての成長や人生の豊かさにつながる最高の武器となります。あなた自身の体験や想いを言葉にして、ぜひ自信を持ってアピールしてください。
体験談・成功事例の紹介

1.ゲームで身につけたリーダーシップが職場評価に直結した例
IT企業で働くDさんは、学生時代からオンラインゲームのギルドマスターを務めていました。ギルド運営ではメンバーの目標設定や役割分担、トラブル時の仲裁や計画の修正など、まさにリアルなマネジメント経験を積んできました。入社後、新人教育やプロジェクトの進行管理を任されることが多く、「チームの意見をまとめる力」「全体最適の視点」が評価され、若くしてリーダーに抜擢されました。Dさんは「ゲームでの経験がなければ、リーダーシップを発揮できなかった」と語っています。
2.分析力・情報発信力を武器にキャリアチェンジ成功
メーカー勤務のEさんは、戦略シミュレーションゲームが趣味。複雑なゲームシステムを研究し、効率的な攻略法や自作の解説記事をSNSやブログで発信してきました。この「分析力」と「情報発信力」が上司に認められ、商品開発チームに異動。市場調査やプレゼンテーション資料作成、データ分析業務などで活躍し、キャリアの幅が大きく広がったそうです。
3.ゲーム仲間の縁が新ビジネス立ち上げにつながった例
フリーランスのFさんは、趣味のオンラインゲームをきっかけにSNSで知り合った仲間と意気投合。ゲーム内イベントの企画やコミュニティ運営を重ねるうちに、自然とリーダーシップやイベント進行力、ネットワーク構築力が養われていきました。その後、知人と共に新しいWebサービスを共同開発し、ゲームで培ったチームワークや発想力がビジネスの成功につながったそうです。「好きなことが思わぬキャリアの扉を開いてくれた」と語っています。
4.趣味を通じて仕事も人生も豊かになった私の体験
私自身も、ゲーム趣味を通して多くの成功体験と人間的成長を感じてきました。学生時代は対人ゲームに苦手意識がありましたが、協力型オンラインゲームを始めてからは「相手の意見に耳を傾ける」「分かりやすく自分の考えを伝える」「トラブルが起きたとき冷静に対処する」といったスキルが自然と身につきました。
社会人になってからも、チームでの難易度の高いプロジェクト進行や、職場のコミュニケーションでゲームでの経験が大いに役立っています。特に“失敗を恐れずに何度もチャレンジする姿勢”や“全員で目標を達成したときの達成感”は、仕事でも大きなモチベーション源になっています。ゲームを通して得た人脈が、思わぬビジネスチャンスやプライベートの充実にもつながっています。
5.依存傾向を克服し自己管理能力を向上させた事例
一時期、毎日深夜までゲームに没頭し、生活リズムが崩れかけたGさん。体調不良や仕事のミスが増えたことで「このままではいけない」と気づき、自分でルールを作ることに。平日は1時間まで、休日は家事や用事を終えてから、など明確な区切りを設けたことで生活が安定し、仕事への集中力やパフォーマンスも回復。以降は“計画的に遊ぶ力”を逆に自己PRとして伝えられるようになり、「自己管理できる人」として面接や昇進でも高評価を得られるようになりました。
このように、ゲーム趣味を通じて多くの社会人がスキルアップやキャリアの幅を広げ、人生を豊かにしています。体験談や事例を交えながら、自分自身の強みや成長ストーリーをぜひアピールしていきましょう。
おすすめのゲーム一覧(社会人・自己成長・コミュニケーション重視)

ゲーム趣味を仕事や自己PR、コミュニケーション強化に活かしたい方に向けて、“成長できる・仲間とつながれる・語れる”おすすめタイトルをジャンルごとにご紹介します。
【1. チームワーク・リーダーシップが磨ける協力型オンラインゲーム】
● ファイナルファンタジーXIV(FF14)
MMORPGの代表格。大人数での協力プレイやギルド運営、チャット・ボイスでの連携が必要。社会人にも人気で、職場の“共通の話題”になることも多い。
● モンスターハンターライズ/モンスターハンターワールド
4人までの協力プレイで役割分担や戦略的連携が求められる。失敗してもみんなで再挑戦できる達成感が魅力。
● Apex Legends
チームバトル型FPS。即断即決の判断力・状況把握・ボイスチャットでのコミュニケーション力を鍛えられる。
【2. 論理的思考・戦略力を磨くゲーム】
● Civilization VI
ターン制の戦略シミュレーション。長期的な計画・資源管理・交渉力などビジネスにも役立つ思考が身につく。
● 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
アクションと戦略、瞬時の判断が鍛えられる。友人・同僚との対戦で“交流”も深まる。
● スプラトゥーン3
戦略・連携・情報共有を楽しみながら、短時間でもプレイできるため忙しい社会人にも最適。
【3. コミュニケーション・人脈づくり重視ゲーム】
● Among Us
心理戦とコミュニケーション力が問われるパーティゲーム。リモート飲み会や職場レクリエーションにもおすすめ。
● Minecraft
クリエイティブな共同作業やワールド作りが楽しめる。オンライン・オフライン両方で人間関係が広がる。
● どうぶつの森シリーズ
“癒し”と“ゆるやかな交流”が楽しめる。家族・恋人・友人と一緒に遊びやすく、幅広い年齢層に人気。
【4. 自己成長・達成感が得られる一人用/RPG・アクション】
● ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド
探索・問題解決・自分のペースで挑戦と成長を楽しめる。自由度と達成感が魅力。
● ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて
ストーリー・戦略・チーム育成と多彩な楽しみ方。自己達成感・考える力が養われる。
● SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
高難度アクションで「失敗→試行錯誤→成功」の自己成長サイクルを体感できる。
【5. 生活・健康・自己管理系のモバイルゲーム】
● ポケモンGO
● Fit Boxing 2(Nintendo Switch)
家でも外でも体を動かしながらプレイ。運動不足解消&ストレス発散に最適。
● Ring Fit Adventure(Nintendo Switch)
筋トレ×RPGで健康管理とゲームを両立。
● Brain Out(ブレインアウト)
スマホで遊べる脳トレパズル。論理力や発想力を気軽に鍛えられる。
【6. 短時間プレイ&仕事・生活との両立がしやすいゲーム】
● TETRIS(テトリス)/ぷよぷよ
短時間で集中力をリフレッシュ。忙しい社会人にもぴったり。
● ポケモンGO
外出・健康増進・交流も兼ねて楽しめる位置情報ゲーム。職場や地域での話題作りにも◎。
【7. eスポーツにチャレンジしたい方に!】
● VALORANT(ヴァロラント)
世界中で大人気の5vs5タクティカルFPS。eスポーツ大会も盛んで、プロを目指す人から趣味の社会人まで幅広い層が参加。
● League of Legends(LoL)
世界最大級のeスポーツタイトル。戦略・役割分担・チームワークが鍛えられる。
● eFootball 2024(旧ウイニングイレブン)
サッカーeスポーツの定番。リアルなスポーツ好きにもおすすめ。
● ストリートファイター6
2023年最新作。個人対戦・大会出場の楽しみや、短時間集中にも向いている。
● PUBG MOBILE
スマホ向けバトルロイヤルの人気作。手軽に世界の仲間と競い合える。

Q&A:ゲーム趣味に関するよくある質問と徹底回答
Q1. 「趣味がゲーム」と言うのは就職や転職活動で不利になりませんか?
A1. 一部の業界や年配の採用担当者の中には「ゲーム=遊び」「仕事と関係ない」と捉える方もいますが、現代ではその考え方も急速に変化しています。ポイントは“単なる娯楽として伝えるのではなく、ゲームで培ったスキルや経験を、仕事にどう活かせるかを具体的に説明できるか”です。たとえば「リーダーシップ」「チームワーク」「情報分析力」「課題解決力」など、ビジネスで重宝される力を強調してアピールすると、むしろ好印象を与えることが可能です。実際に「ゲーム趣味をしっかり自己PRできたことで内定が決まった」「チームビルディング力を評価された」という成功事例も増えています。
Q2. ゲーム趣味が“依存”や“生活リズムの乱れ”につながることはありませんか?
A2. ゲームは没頭しやすい趣味でもあるため、時間や健康管理が大切です。特に社会人は、仕事や家庭とのバランスを崩さないよう「平日は1日1時間まで」「休日は家事・用事の後にプレイする」など、自分なりのルールを設けるのが効果的です。また、家族やパートナー・友人と話し合って理解を得るのも大切。ゲームのしすぎで体調や業務に支障が出た経験がある方でも、自己管理を徹底しバランスよく楽しむことで、逆に「計画的に遊べる力」「自己制御力」が強みとなり、社会人としての信頼度も上がります。
Q3. 面接で「趣味がゲーム」と伝えた際、どのような言い換えや説明が効果的ですか?
A3. 「趣味はゲームです」とそのまま伝えるよりも、「協力型オンラインゲームでチームリーダーを経験」「戦略シミュレーションで分析力を磨いた」など、具体的な内容や得たスキルを盛り込むと説得力が格段に高まります。また「新しいジャンルに挑戦することでチャレンジ精神が鍛えられた」「失敗を繰り返しながらも継続して目標達成に取り組んだ」など、自分の成長ストーリーとして語るのも効果的です。面接官がネガティブに感じている様子なら、「情報収集力」「チームビルディング力」「異文化理解」など、どんな職種にも活かせる点を強調しましょう。
Q4. ゲーム趣味で得た友人やネットワークは社会人生活でも役立ちますか?
A4. 非常に役立ちます。オンラインゲームやSNSでつながった仲間とは、仕事や生活で困ったときの相談相手や新たな情報源、時にはビジネスチャンスにもつながる“人脈”となります。実際に「ゲーム仲間と起業した」「異業種の人と知り合い新たなキャリアが開けた」など、趣味から生まれた縁が人生の転機になるケースも多々あります。また、コミュニケーション力や多様性への理解も深まり、リアルな職場や日常生活でも大いに役立ちます。
Q5. ゲーム趣味を仕事や自己PRにどう活かしたら良いか迷っています。具体的な活用方法は?
A5. まずはゲームを通して得た経験や成長を紙に書き出し、「どんなスキルが身についたか」「どんな場面で役立ったか」を整理しましょう。たとえば「仲間と目標を達成する過程で学んだ協力や調整力」「失敗から何度もチャレンジし続ける粘り強さ」「効率的に情報収集し素早く意思決定する力」など、具体的なエピソードを自己PRや面接で伝えるのがおすすめです。また、仕事で活きた実体験や成果を積極的に共有すると、趣味が“信頼できる自己成長の証拠”として説得力を持ちます。
Q6. ゲームを通じて得られる“最大のメリット”とは?
A6. ゲーム最大のメリットは「自己成長と新しい人脈の獲得」です。論理的思考や瞬発力、柔軟な対応力、コミュニケーション力、国際感覚など、現代社会で求められる多様な力が養われます。さらに、年代や国籍を超えて新しい仲間と出会い、人生の視野や価値観も広がります。仕事のストレスをうまく発散できるのも、社会人にとって大きな利点です。
Q7. ゲーム趣味を堂々と公言することに不安があります。自信を持つには?
A7. ゲーム趣味を公言することに最初は勇気がいるかもしれませんが、社会の価値観は急速に変化しています。大切なのは「どんな経験や学びを得て、それをどう活かしているか」を自分の言葉で語れること。周囲の評価を気にするより、まず自分自身が“誇りと責任を持って”趣味を楽しむ姿勢が、最終的に説得力や好印象につながります。体験談や実績を積極的に発信することで、共感や応援の声が増え、自信も自然とついてくるはずです。
Q8. ゲームに偏見を持つ家族や上司とのコミュニケーションは?
A8. まずは「なぜゲームが好きなのか」「どんなスキルや人脈が得られているのか」など、客観的なメリットを丁寧に伝えることが大切です。例えば「協力プレイで培ったチームワークが仕事で役立った」「ゲーム仲間との交流が新しい仕事につながった」など、具体的な成果や成長エピソードを交えることで、理解や評価が得やすくなります。時間管理や自己制御に努め、社会人として責任を持って趣味と向き合っている姿勢も一緒に伝えましょう。
【まとめ】

ゲーム趣味は、現代社会の中で急速に評価が高まりつつある個性豊かなライフスタイルの一つです。かつては「子供の遊び」「仕事に役立たない」といった偏見も根強くありましたが、今やゲームを通じて得られるリーダーシップ、課題解決力、チームワーク、情報収集力、コミュニケーション力、自己管理能力など、社会人として不可欠なスキルやマインドが身につくと、多くの企業が認識し始めています。
実際に、ゲームで培った能力を自己PRや面接で前向きに語ることで、内定やキャリアアップのきっかけをつかんだ成功例も増えています。また、ゲームを通して得た友人や人脈が、ビジネスや人生の転機を生み出すケースも珍しくありません。依存や生活リズムの乱れといったデメリットも、自己管理やバランス感覚を持つことで十分に克服・コントロールできます。
働き方改革やリモートワークの普及、グローバル化が進むこれからの時代、趣味を持つこと自体が“人間的な魅力”や“主体性”として重視される流れはますます強まります。ゲーム趣味は「集中力や創造性の向上」「ストレス発散や心の健康維持」「多様な人材・価値観との交流」など、現代人のライフバランスに欠かせない役割を果たしています。
ポイントは、趣味を“ただの息抜き”で終わらせず、「自分にどんな成長や経験があったのか」「社会でどのように活かしているのか」を具体的なエピソードや事例とともに語ること。その積み重ねが、自信となり、周囲からの信頼や評価にもつながります。
どんな趣味であっても、活かし方や向き合い方次第であなたの人生とキャリアは無限に広がります。ゲームを通じて得た体験や学びを、ぜひこれからの仕事や自己PRに積極的に活かし、より豊かな社会人生活を実現してください。
最後までお読みいただきまして
ありがとうございました。